


ブログメニュー
プラットフォーム事業部
2025.10.06
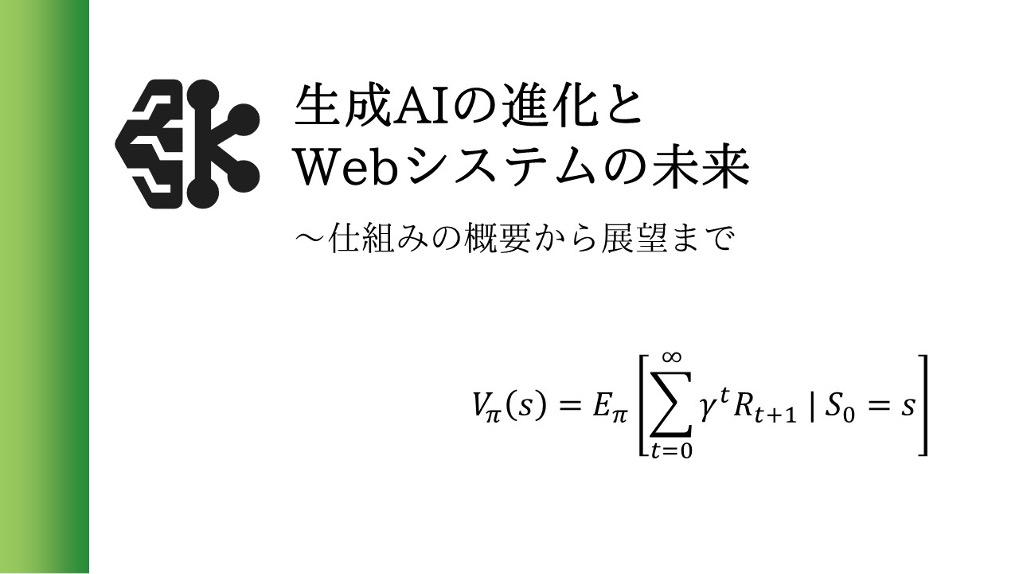
皆さま、こんにちは。
グローバルウェイのNです。 今回は、生成AIとWebシステムの未来について、生成AIの基本を解説するとともに、ビジネスユースの展望をご紹介します。
皆さまは、生成AIと聞いて何を想像するでしょうか。
チャットベースでの文字の生成、画像または動画の生成、業務ツールの操作補助に組み込まれている生成AIの有り様を想像できると思います。
端的に説明すると、生成AIはテキスト、画像、音声、動画といったコンテンツを生成できる人工知能システムのことです。テキストを主として処理する生成AIは大規模言語モデル(Large Language Model、LLM)を利用した人工知能システムの一種となります。人工知能の定義は定まっていないところもありますが、人の手で作られた知能のことを指しますので、テキストを主として処理する生成AIは「人の手で作られた大規模言語モデルによる知能」と言えます。
ここでは、生成AIという言葉の定義を追求するのではなく、テキストを主として処理する生成AIにフォーカスして、その仕組みと進化を紹介していきます。
生成AIにおいて大規模言語モデルは、入力された文脈に基づき出力となる文脈を生成します。ある文字または単語をパラメータとして扱い、このパラメータの続きを決定していく仕組みによって、文章を生成できます。
この仕組みは、パラメータから続きのパラメータを決定することに必要となる既存の文脈データを学習した結果を積み重ねていくので、小規模な学習量では結果に文脈または知識の偏りを生じることがあります。
大規模な学習量では、学習結果に一般知識とともに、様々な文脈の形を含んでいますので、大規模言語モデルは学習結果の恩恵を多く得られるというわけです。
近年では、そうした基本となる仕組みに加えて様々な工夫を加えています。
一例としてTransformerフレームワークを紹介します。
初期の大規模言語モデルでは学習データに単純な比例を示す統計的なモデルとなっていました。与えた学習データを単純に比例していくため、学習データの増加に伴って偏りのない文脈を出力として示します。一方で平均に留まった学習結果になりがちですので、一定の学習データ量に達すると性能向上を望めなくなります。
Transformerフレームワークは、Attention機構と呼ばれる仕組みを軸として文字や単語といったパラメータの重要度を決定する仕組みを集めた枠組みです。このフレームワークの登場により、これまで難しかった、データの量ではなく質によって性能を決定することを実現し、Transformerフレームワークとその亜種に基づいた高性能な大規模言語モデルの台頭する時代に突入したのです。 ChatGPTに組み込まれている、テキストを主として処理する生成AIは、Transformerフレームワークとその亜種に基づく大規模言語モデルの一つです。
高性能な大規模言語モデルの台頭により、意味を持った文脈の入力を与えることさえ出来れば何らかの処理を実行可能とすることになりました。入力した文脈から出力するにとどまらず、画像処理、音声処理といった各処理の橋渡し役として大規模言語モデルは有用なのです。
文脈処理に特化したAIを用いて、画像処理または音声処理に特化したAIをまとめることで、今日ChatGPTに代表される、画像と編集指示の文脈の入力により出力として編集後の画像と処理内容の文脈を得られるようなツールは実現されています。
汎用性の観点から、画像処理といった特定の処理に特化したAIを「弱いAI」、画面上のツールの操作方法を理解しながらクリックまたはキータッチといった操作から適切なものを選んで実行する特定の処理に特化しないAIを「強いAI」と呼びます。 大規模言語モデルを持った生成AIは、以前に見られた特定の処理に特化したAIに比べて汎化したことで「強いAI」に近づいたのではないでしょうか。
生成AIの汎化に伴って、様々なシステムへの組込みのメリットは大きくなったと言えるでしょう。組込みに際して、機密データの扱いを定義し、順守させる仕組みを構築して、意図しない動作のリカバリを準備するコストを考えると、社会全体におけるナレッジとユースケースの蓄積を待ってから組込みに向けて動き出そうとする状況はしばらく続くと考えられます。
しかしながら、マルチモーダルを実現した生成AIは人とシステム間でクリックやタイピングで行われてきた操作に文脈のやりとりを加えることで、さらに進化するでしょう。人とシステムのコミュニケーションと言えるほどの柔軟性を、システムに持たせる社会に進んでいくと仮説を立てることができます。
その始まりは、組込みといった変更への柔軟性を維持しやすい、標準仕様に基づいたWebシステムからではないかと予想しています。
これまでヘルプサイト構築、サポートセンター運用に依存していたWebシステムのガイドは一新されて、特定の操作を画面上にてナビゲートするといった汎用ユーザガイドを提供することが可能です。Webシステムの利用ユーザと伴走するコンサルタントのような汎用ユーザガイドの提供を生成AIは強力に後押しすることになります。
いかがでしたでしょうか。
今回は、生成AIの概要とWebシステムへの組込みについてご紹介しました。
これから生成AIはもっと身近になりますが、どこまで深く仕組みを理解しているかで、得られる効果に差が出ます。仕組みを深く理解して成果を出せるエンジニアを求めるシーンは、これから確実に増えていくのではないでしょうか。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。